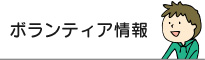
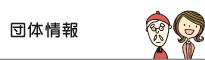
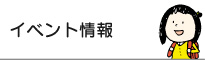
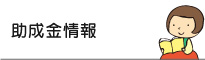
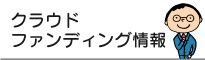
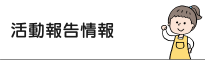
A1 「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語では「非営利組織」と呼びます。広い意味では自治会や労働組合なども含まれますが、一般的には市民活動団体やボランティア団体、または特定非営利活動促進法(NPO法)により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)などを指すことが多いようです。 また、国内で活動する民間のこうした団体をNPOというのに対して、海外で活動している団体をNGO(Non-Governmental Organization=非政府組織)と呼び分けることが一般的です。
また、「非営利」というと、対価を得ずに無償で行う活動というイメージがありますが、そうではなく「利益を分配しない」ということです。
A2 平成7年(1995年)1月に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに「ボランティアや社会貢献活動を目的とした団体にも法人格を」と、平成10年(1998年)に特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。これにより、NPOの中で都道府県知事(島根県では一部市町村に権限を移譲)の認証を受けた団体を特定非営利活動法人(NPO法人)といいます。 NPO法人になると法人の名義で契約ができるなどのメリットもありますが、義務もあります。
A3 特定非営利活動とは以下に掲げる20分野のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動です。
A4 内閣府によると、認証とは「ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているもの」とされています。 NPO法では、いわゆる社会福祉法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度と異なり、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されています。特定非営利活動促進法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、所轄庁は認証しなければなりません。 また、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。 公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを県民一人一人が判断することが求められています。
A5 NPO法人になると、法人名で契約や資産の所有・管理ができるようになります。また、社会的信用が増すことも期待できます。しかしながら、団体に対する信用は法人格を持ったからといって得られるものではなく、しっかりとした活動実績から得られるものだと心得ておきましょう。
その一方で、NPO法に基づいた法人運営や書類提出が義務付けられます。加えて、納税や登記など、各種法令等を守る必要があります。これらの事務的な負担を担えるかどうかについても事前に確認しておきましょう。
そして、活動を継続させるためには、しっかりとした事業計画が大切です。
NPO法人になると得られるメリットや、法人化に伴う義務を理解したうえで、本当に法人化が必要かどうか、よく話し合ってみましょう。
A6 法人になれば、当然各種の納税の義務が発生します。国税のうち、法人税については本来事業に係る所得(会費収入、寄附金収入など)には課税されませんが、収益事業に係るものについては一般の企業と同じように課税されます。 具体的には、管轄の税務署で確認ください。
また、県税については、島根県では一定の要件に該当する場合には、法人の県民税均等割や不動産取得税、自動車取得税の課税免除の措置がとられています。詳細は島根県NPO活動推進室へお問い合わせください。
A7 法人となれる要件は次のとおりです。
A8 「営利を目的としない=利益をあげてはいけない」ということではなく、上がった収益を法人の構成員たる社員等に分配してはならないということです。NPO法人が雇用している職員に対して給与を支払うことは何ら問題ありません。利益は特定非営利活動の事業費等にあてることになります。
A9 ここでいう「社員」というのは、法人の構成員であって「総会で議決権をもつ会員」のことです。いわゆる会社の社員のように雇用契約を結んでいる「職員(従業員)」とは違います。
NPO法人は広く市民に開かれた運営をしなければならないとの観点から、この「社員」の資格の得喪に関して不当な条件をつけることはできません。例えば住所や出身校、性別、思想等によって会員資格を制限することは「不当」と見なされるでしょう。
A10 役員は最低でも理事3人、監事1人が必要です。また、配偶者や3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてはならないことになっています。その他、役員報酬を得る者は役員総数の3分の1以下でなければなりませんが、役員報酬は、雇用契約に基づく職員の給与とは異なります。 したがって、理事兼事務局長という人が、給与のみをもらっていれば、「役員報酬を得る者」には含まれません。
A11 まず、2人以上の発起人による設立準備委員会や発起人会などにより、定款や設立趣旨書、活動予算書などの原案を作成し、設立総会を開催してこれらを承認するとともに役員等を決定します。
申請に必要な書類については島根県NPO活動推進室のNPO法人の設立・運営の手引きをご参照ください。
また、事業開始に必要な許認可や届け出がないか確認が必要です。
なお、以下のことをじっくり検討されることをお勧めします。
A12 認証申請が所轄庁に受理されると、申請書類が2週間縦覧されます。問題がなければ、縦覧期間終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行なわれます。したかって、申請から決定まで、最低でも2ヶ月かかることになります。
ちなみに、NPO法人は、主たる事務所の所在地で登記することによって成立します。また、登記が完了すると速やかに所轄庁にその旨を報告しなければなりません。
なお、認証申請の詳細については島根県NPO活動推進室のNPO法人の設立・運営の手引きをご参照ください。
A13 申請窓口は下記の島根県もしくは市町村になります。
参 照 : NPO法人申請窓口